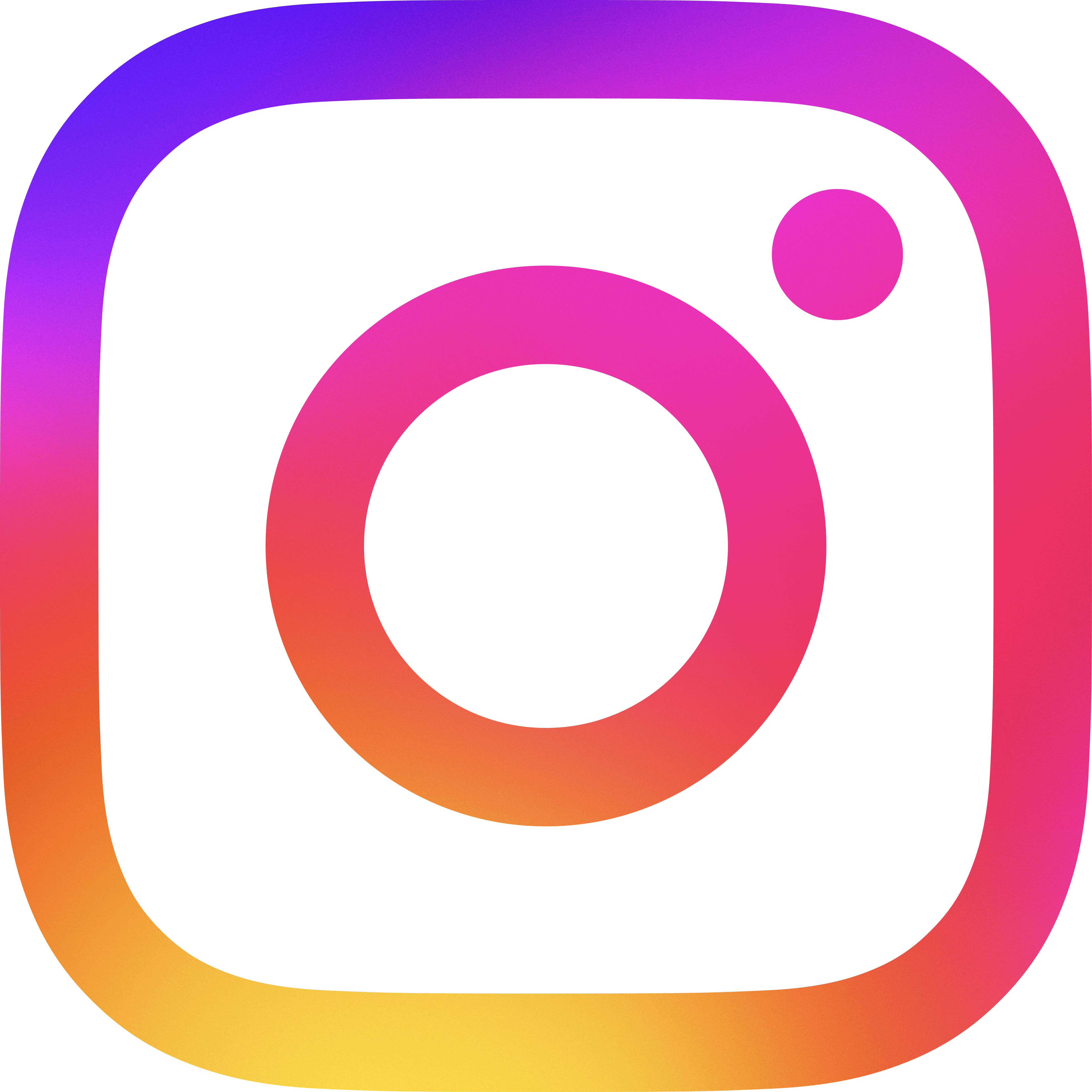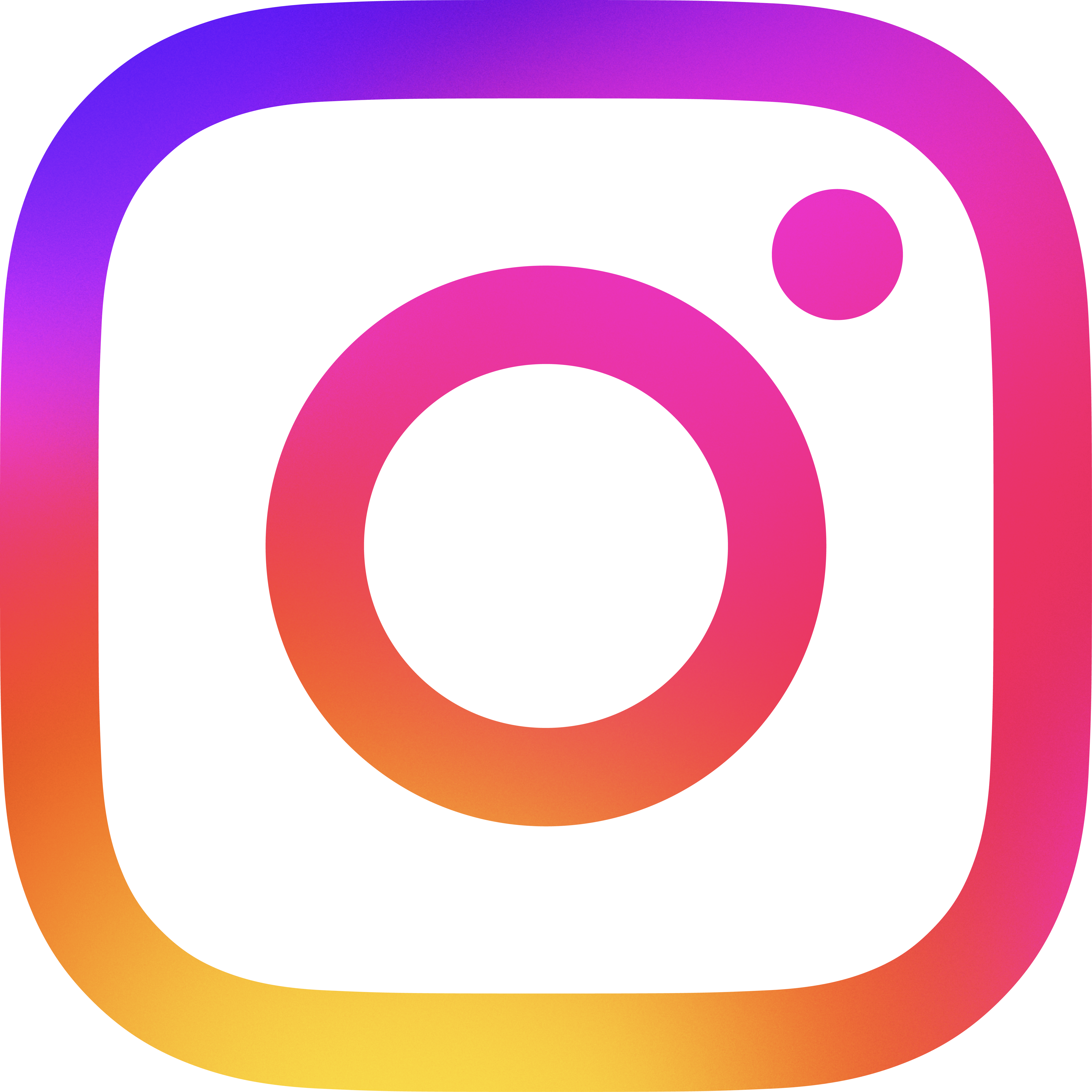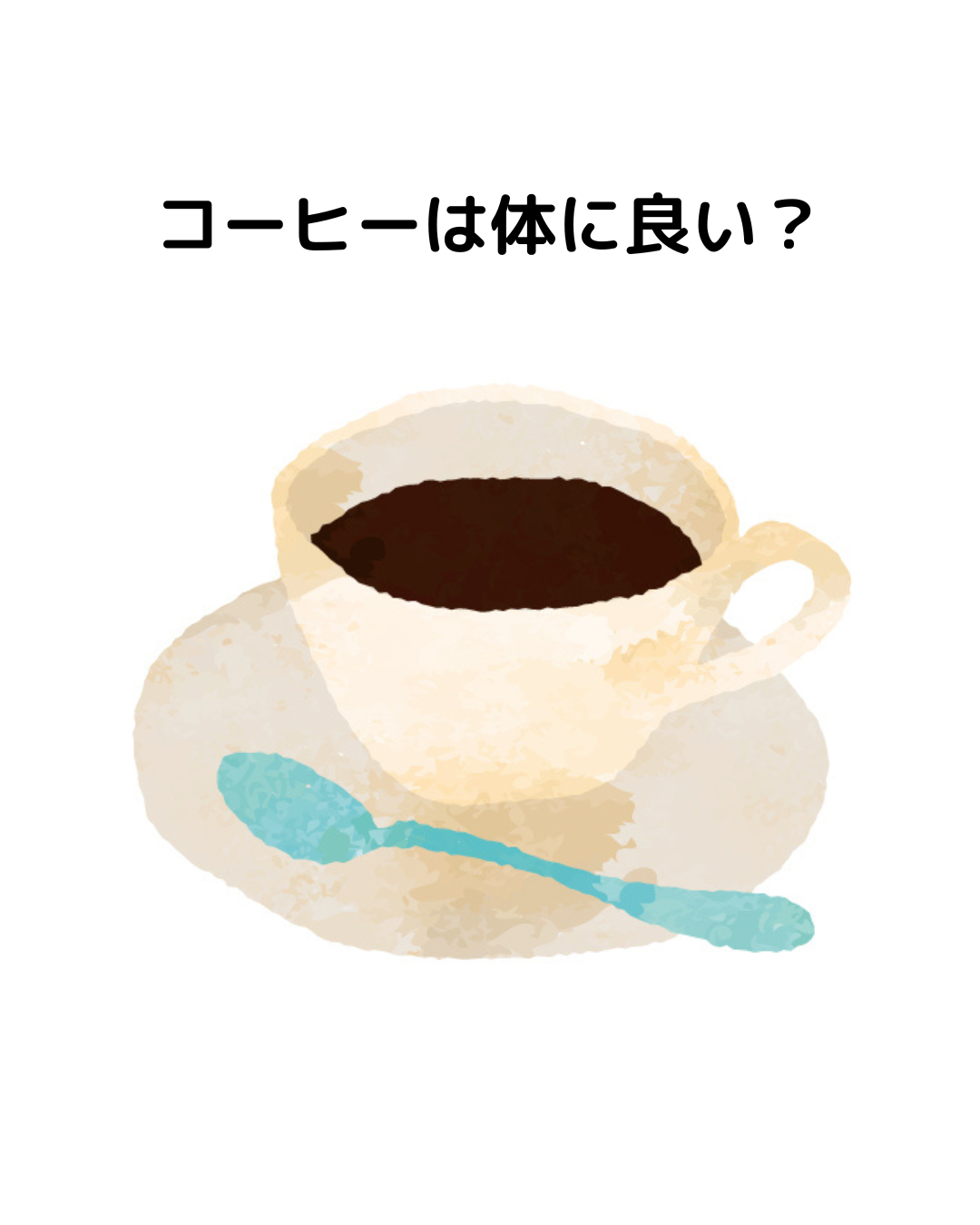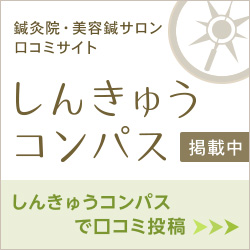先日、通っている茶道教室で“初釜”に行ってきました🍵
新年をお祝いする、1年で最初のお茶会です。
キリッとした冬の空気の中、釜から立ちのぼる湯気を見つめながらお茶をいただく…。
年末年始でバタバタしていた心身が、スッと落ち着く贅沢なひとときでした🌿
実はこの「お茶の時間」、東洋医学的にも今の時期にぴったりな理由があるんです💡
■お茶席に隠れた「1月の養生」
1. 「ぼーっとする時間」が最高の養生
お正月は何かと「気」が忙しく動き回り、のぼせや疲れが出やすいもの。
静かにお茶の音に耳を傾けることで、上がりきった「気」が落ち着き、自律神経のバランスを整えてくれます。
2. 抹茶の「苦味」が心に効く!
東洋医学で抹茶の「苦味」は、血流を司る「心(しん)」を元気にする味。
新年の活動に向けたパワーを内側からチャージしてくれます💪
3. お正月疲れの胃腸をスッキリ
ご馳走やお餅で重たくなったお腹に、抹茶のキリッとした苦味が嬉しい刺激に。
デトックスを助けて、体をシャキッとさせてくれます。
最後は急遽お点前をすることになって、緊張でのぼせてしまいましたが(笑)、
貴重な経験をさせていただきました✨
皆さんも、お気に入りのカップで温かいお茶をゆっくり飲む「自分への5分間」を作ってみてください🍵冬の体がぐんと楽になりますよ~☺❄