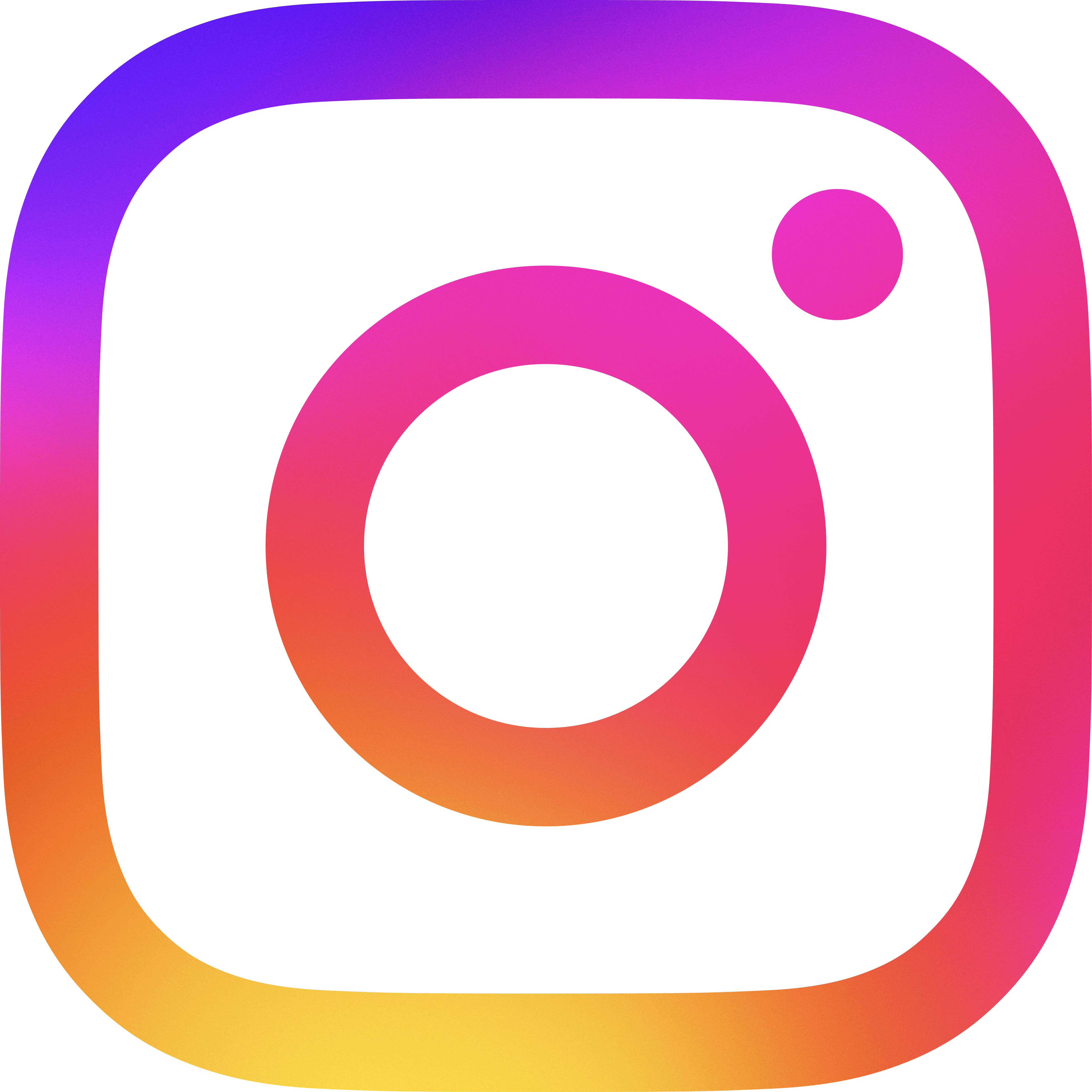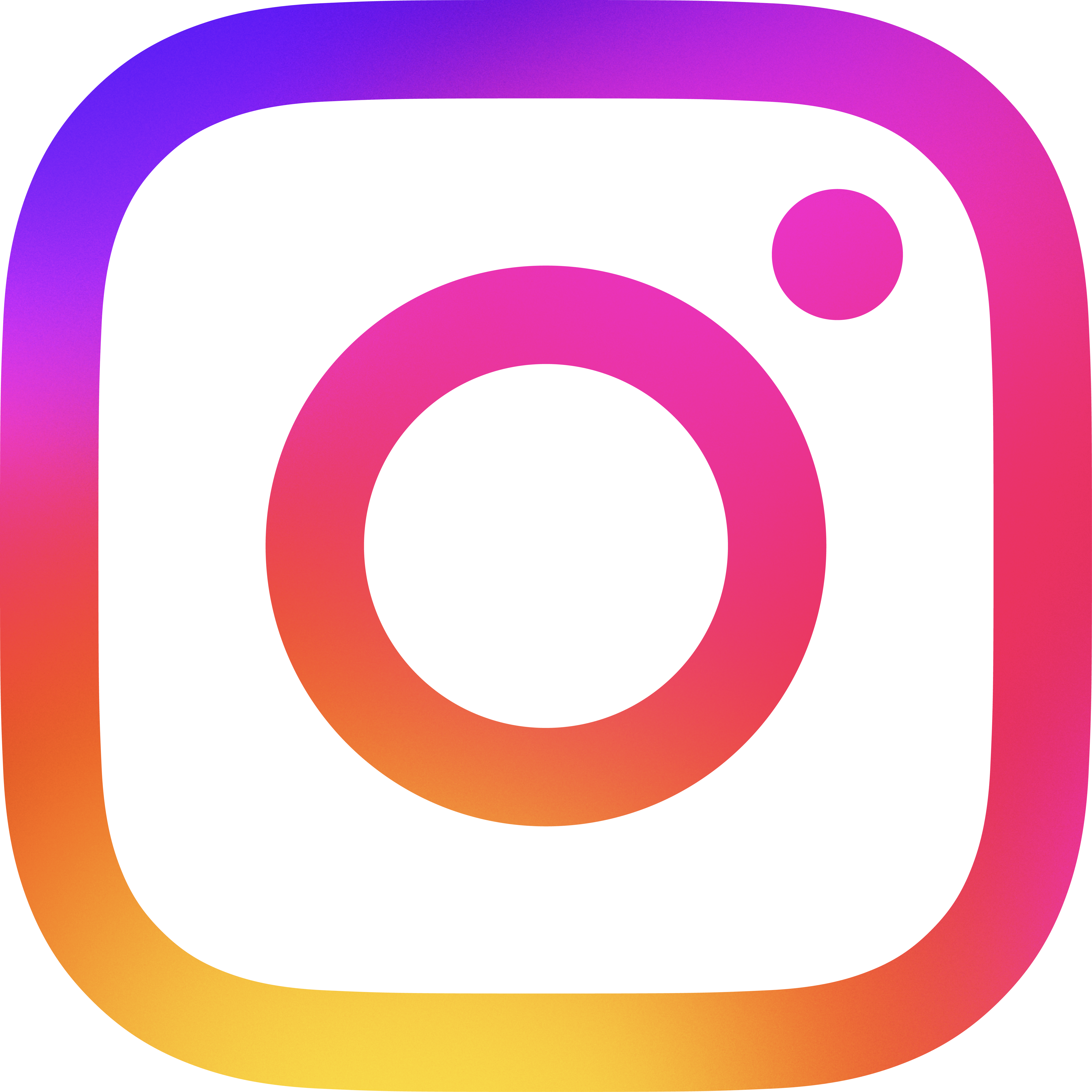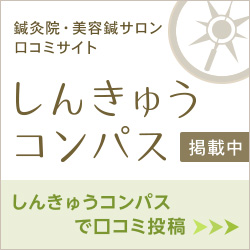その肩こり、「肝」の疲れかも? 左右差の原因と鍼灸でのアプローチ
デスクワークや日々のストレス、スマートフォンの長時間利用などでつらい肩こりにお悩みではありませんか?
整体やマッサージに行ってもすぐに元に戻ってしまう…。
もしかしたら、そのしつこい肩こり、東洋医学でいう『肝』の疲れと関係があるのかもしれません。
■なぜ肩こりに「肝」が関係するの?
東洋医学の『肝』は、現代でいう「肝臓」の働きだけでなく、もっと広い役割を持っています。肩こりとの関連で特に重要なのが以下の3つです。
1. 「気」の流れをコントロール
『肝』は全身の「気」の流れをスムーズにする役割があります。
精神的なストレスやイライラを感じると、この気の流れが滞って熱がこもったり、筋肉が緊張しやすくなります。特に首や肩はストレスの影響が出やすい場所です。
2. 「血」を貯蔵し筋肉を栄養する
『肝』は「血」を貯蔵し、必要に応じて全身に供給します。過労や睡眠不足、栄養の偏りなどで『肝』の血が不足すると、筋肉や腱に十分な栄養が行き渡らず、硬くなったり、こわばったりしてしまいます。
3. 筋肉・腱の働きを調整
「肝は筋を主る」と言われ、筋肉や腱の柔軟性やスムーズな動きは『肝』の状態に左右されます。つまり、ストレスや疲労で『肝』のバランスが崩れると、気の流れが滞ることで血が不足して筋肉が硬くなり、その結果で肩こりとして現れやすいのです。
■右肩こり?左肩こり?左右差に意味はある?
「右肩だけ」「左肩だけ」と、こり方に左右差がある場合、いくつか考えられることがあります。
〇東洋医学的な見方
「左は血、右は気」と関連付けたり、肩周辺を通る経絡の状態から解釈することもあります。
〇生活習慣・体の使い方
原因として、こちらが非常に多いです。利き腕、バッグを持つ肩、寝る向き、PC作業の姿勢(マウスの位置など)といった日頃の癖で、左右どちらかに負担が偏っている可能性が高いです。
〇内臓からの関連痛(要注意⚠)
右肩のしつこい痛みは肝臓・胆嚢、左肩の場合は心臓・膵臓などの問題が隠れている可能性も否定できません。
特に、安静にしていても痛んだり、痛みが非常に強かったり、徐々に悪化する状態であったり、他の症状(胸痛、腹痛、吐き気、発熱など)を伴う場合は、自己判断せず、必ず医療機関を受診してください🏥
■鍼灸でできる根本的なアプローチ
もし、生活習慣の見直しやストレッチだけでは改善しない場合、鍼灸を試してみるのも良い方法です💡
鍼灸は、単に硬くなった筋肉を緩めるだけでなく、肩こりの背景にある根本原因に働きかけます🌼
例えば…
・『肝』のバランス調整
ストレスや疲労で乱れた『肝』の機能を整え、気の流れをスムーズ にします。
・気血の巡り改善
全身の気血の巡りを良くし、筋肉にしっかりと栄養を届けられるようにします。
・自律神経の調整
鍼灸の刺激は自律神経のバランスを整え、心身のリラックスを促し、ストレスによる筋肉の緊張を和らげます🌿
■まとめ
つらい肩こり、特に左右差がある場合、その原因は「肝」の疲れとなるバランスの乱れ、生活習慣、そして時には内臓の問題まで様々です。
まずは、心配な症状があれば医療機関での相談が大切です🏥
その上での鍼灸は、体の内側からバランスを整え、肩こりの根本改善を目指す有効な手段となります🌷
長引く肩こりにお悩みの方は、ぜひご相談ください☺♪